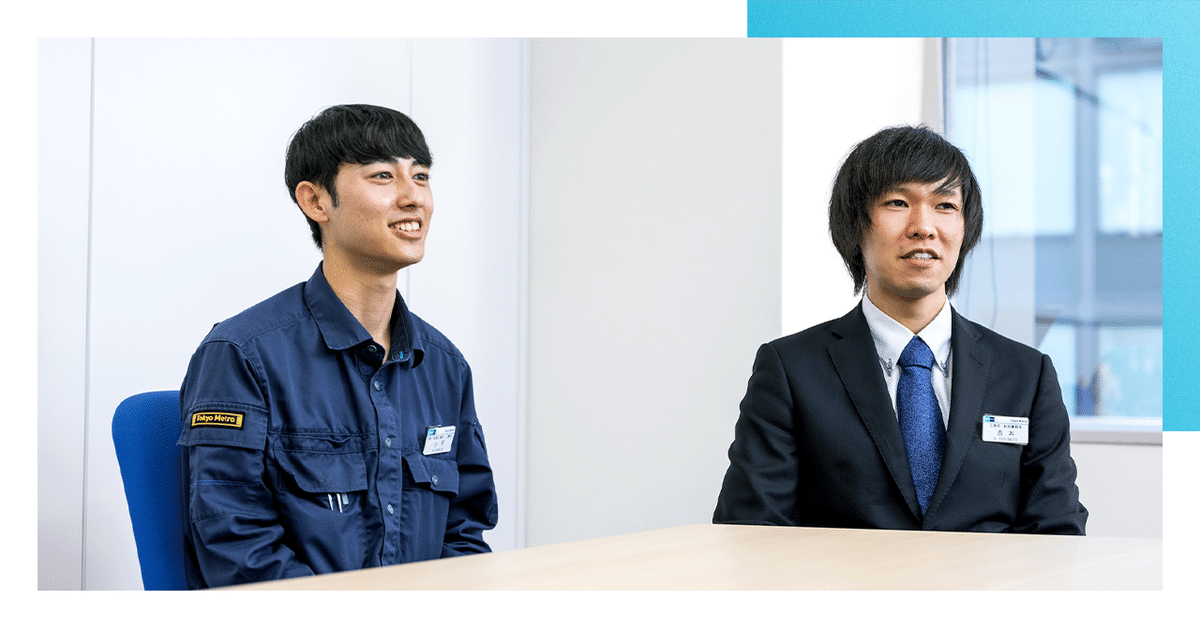
【特集Vol.02】ホーム看板に求められる、見やすさへのこだわり。
駅のホームで、自分が何番線にいるのかを知りたいとき、乗り換えたい路線の方向を知りたいとき、ふと目を向けるのが天井から吊り下げられた案内看板ではないでしょうか。一見すると何気なく設置されたように思えますが、お客様が見やすいよう、確かな安全につながるよう、現場のアイデアと工夫から生まれたこだわりがあります。
今回は“模型”がカギとなった新たな取組み「ホーム看板レイアウト」の検証に携わった担当者の2人に話を聞きました。

最も大切なのは、お客様が見やすいこと

工務部 建築計画課/吉本 良平(写真右)
吉本:お客様がホームのどこにいても、必要な情報を届けることがホームに設置された看板の役割です。だからこそ、看板がホーム上の柱や他の看板と被ってしまってよく見えない、近づかないと見えないといった場所にあってはなりません。快適に駅や列車をご利用いただくためにも、私たちはお客様の見やすい場所に看板を設置することを最も大切にしています。
小平:ホーム上には看板だけでなく、お客様を時間通りに、目的の駅までご案内するための重要な設備が設置されています。ホームを監視するモニターやカメラ、お客様の乗降の終了を伝える戸閉合図表示器、列車がホームに到着してからの時間を示す運行指示器など、これらの設備を運転士、車掌、駅係員は確認し、安定的な運行につなげています。つまり、どの設備にも“死角”があってはならないのです。
突然の発着ホーム変更の一報。
新たな取組みへの決意
吉本:「車掌が確認するモニターにホーム看板が写り込んでしまい、運転に支障が出ている」という連絡が入ったのは2019年のことです。東京メトロのすべての運行管理を行っている総合指令所からの一報で、確実に安全が確認できるモニターを使用するために列車の発着番線を急遽変更したことが明らかになりました。突然の発着ホームの変更にお客様が迷ったり、焦ったりしてしまったのではないだろうか。私たちはお客様にご迷惑をおかけしてしまったことを真摯に受け止め、今後このような事態が起こらないよう新たな取組みへと動き出しました。
どこからも見やすいホーム看板と安定的な運行のための設備、ホームにはその両方があってこそ、お客様の快適さや便利さにつながってきます。そこで私たちは互いに支障をきたさないため、ホームに新たな看板を設置する際の確認方法を見直すことから始めました。これまで東京メトロでは、ホーム看板の設置前は、事前の現地調査を基に作成した図面を見て、看板の設置位置を確定していました。しかし、図面はあくまでも平面的なイメージであり、看板を設置する高さや見る角度によって設備同士が邪魔にならないかどうかは、完成後の状況を立体的にイメージすることでしか補えなかったのです。
また、夜間の看板設置工事が完了した後には、実際の始発列車で車掌が確認を行っていたのですが、たとえ看板と安定運行のための設備の重なりが見つかったとしてもすぐに対応することはできません。お客様からホーム看板が見えることはもちろん、運転士や車掌、駅係員それぞれの立ち位置から必要な設備は見えるだろうか?そんな不安を残したままでは快適さも、さらには確かな安全もお届けすることはできない。一番視覚的にわかりやすく、社内の関係者全員が一緒に見て、確実に確認できる方法はないだろうかと考えた結果、ホーム看板の“模型”を使ったレイアウト検証を行うことにしました。

社内の関係者が一堂に揃い、
模型を使ってリアルに現場検証

小平:模型は自分たちで作りました。形状や寸法は看板ごとに異なるため、いろいろな駅で対応できるよう、幅を自由に調整できるようにしたことがポイントですね。
吉本:この模型を使ったホーム看板のレイアウト検証は方南町駅で最初に行いました。運転士、車掌、駅係員、ホーム看板設置工事の担当者や工事を行う取引先の方々が集まり、ホーム看板の設置位置に模型を掲げ、各設備の視認性に影響がないか確認することからスタート。運転士や車掌は列車を安定運行させるという視点から、ホーム監視カメラが撮った映像がモニター上で問題なく見えるかなどの確認を行いました。
その一方で私たち建築工事担当者はお客様にとって見やすいホーム看板という視点で徹底検証しました。たとえば、ホーム看板同士が近すぎると重なりによって見えなくなってしまうため、駅を利用されるお客様に必要な情報を提供できなくなってしまいます。そこで、既存の看板に対し、模型の高さや距離を変えながら、見える・見えないの合図を出し合い、支障がないかを確認しながら最適な位置を定めていきました。
小平:検証をするにあたってまずは図面でホーム看板が見えづらくなる位置を想定して臨んだのですが、やはり現場に立ってみるとその感覚は違っていて……。ひとつの駅のホームといっても、場所によって設備の設置位置がさまざまであったり、天井の高さが一律でなかったりと、模型を掲げる場所ごとに見え方が違っていたので、それを調整していくことに大変苦労しました。
また、大勢の関係者の方が緊張感をもって臨むなか、限られた時間で検証を円滑に進め、最善の答えを導き出すことは自分にとって大きなプレッシャーでしたね。

部署を超えた連携で、
あらゆる視点から快適さを考えていく
小平:ホーム看板の検証を通して、設備の設置ひとつ取っても多くの部署の視点が必要であることに改めて気づかされました。たとえば天井を張り替える工事であれば、天井に設置されている照明やカメラなどの設備を一度取り外すことになるため、電気や通信設備を管理する部署との連携が求められます。
各部署との連携をより強固にし、あらゆる視点を持つことで、お客様に実感いただける本当の意味での“快適さ”につながります。私は工事監理の担当者として、部署を超え、さらにより良い環境づくりに努めていきます。
吉本:私は建築計画の担当者として建築施設に関する規程を考えることを通じて、常にお客様に便利かつ快適な環境をご提供することを使命としています。また、人材育成担当という立場からも、建築に関わる社員の能力の底上げやお客様への意識向上に貢献することで、その先にいらっしゃるお客様の安心につなげていけたらうれしいですね。

【教えて!看板のギモン】
Q. ホーム看板はどこから見えるように設置されているの?
A. 基本的に、移動しながら見るような吊り下げ仕様のホーム看板は20m手前から、情報量の多い壁に設置された看板は1m手前から確認できるようにしています。
看板は表示スペースの寸法から文字の大きさまで社内のガイドラインで定められています。

Q. エレベーター案内看板にある、色のついたマークはなに?
A. 地上行きのエレベーターが複数ある場合に、それぞれのエレベーターを識別できるようにつけているマークです。長方形の中に書かれたアルファベットは、青色であればブルーの「b」と英語の頭文字を入れています。

※記事の内容は2022年12月の取材時点のものです。

